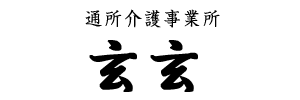サービス内容
「玄玄は、1日の利用定員が最大18名の小さなデイサービスです。
ご利用者お一人おひとりの状態や気分に合わせて、食事・入浴・排泄などの介助やレクリエーションを丁寧に提供しています。
利用者数が限られているからこそ、毎日の小さな変化にも職員全員で気づき、声をかけ合いながらきめ細かな対応が可能です。
その日の“その人らしさ”を大切にしながら、無理なく、心地よく過ごせる時間をつくる──それが玄玄のケアのかたちです。」
サービス提供時間
玄玄のサービス提供は通いの日中のみです(夜間サービスはありません)。
営業日:月曜〜土曜(祝日を除く)
定休日:日曜・祝日。
玄玄で提供している主なサービス
- ご自宅〜玄玄の送迎
- 到着時の健康チェック(バイタル測定等)
- 入浴の介助
- 食事の提供と見守り
- 排泄の介助
- 機能訓練(簡単な体操やリハビリ)
- レクリエーションの企画・実施(季節の遊び、体を動かす活動 等)
医療・介護の専門職による、安心のケア体制
玄玄では、ご利用者さまの健康と安全を守るため、以下のような専門職によるサポート体制を整えています。
玄玄で提供している主なサービス
- 看護師が常勤し、健康管理から緊急対応まで安心を支援。
毎朝のバイタルチェック(体温・血圧など)や服薬管理、緊急時には迅速に医療機関と連携しています。 - 介護福祉士など有資格者が、日々のケアにあたります。
入浴介助、食事・排泄などの身体介助からレクリエーションの実施まで、安心と尊厳を守るケアを行います。 - 少人数だからこそ、スタッフ一人ひとりの変化に気づける体制です。
1日最大18名という小規模な環境であるため、利用者さま一人ひとりの表情や体調の微妙な変化もしっかり把握できます。 - スタッフのスキルアップを積極的にサポート。
定期研修の受講や資格取得を奨励しており、新人には経験豊富な先輩がマンツーマンで指導。安全で確実なケアの提供を通じて、サービスの質を常に高めています。 - 認知症ケアへの配慮にも、常に「そばにいる」
玄玄では、「住み慣れた地域で、いつまでも暮らしたい」という想いを大切にした認知症ケアを心がけています。 - 否定せず、ゆっくり話をお聞きします。
認知症の方が発する「今の気持ち」を大切にし、その人らしさを尊重した対応をします。 - できることは尊重し、できないところは支えるケアを。
「できることは自分で」「できにくいところはそっとサポート」のバランスで、安心感を感じていただける支援を行います。 - 不安な状況には、見守りを強化します。
徘徊などが心配な方には、その日の体調や状態に応じてスタッフの配置や声かけを調整し、安全に配慮した環境づくりに努めています。
このような取り組みを通じて、どんなに小さな変化にもすぐに気づける、身近で温かなケアを提供しています。
INSTAGRAM
Facebook

928
通所介護事業所玄玄
広島市南区東雲二丁目7番17号の地域密着型「通所介護事業所 玄玄」です。
生活とリハビリがつながる介護をめざしています。
スタッフ募集あり(応募はハローワーク:事業所番号3414-616460-5)。
社一帯がパワースポットとなっております。
Japanese real underground CARE organiz
【スタッフ募集(正社員)のお知らせ|通所介護事業所 玄玄】![]()
![]() 広島市南区東雲二丁目7番17号の地域密着型通所介護「通所介護事業所 玄玄(げんげん)」です。
広島市南区東雲二丁目7番17号の地域密着型通所介護「通所介護事業所 玄玄(げんげん)」です。![]()
![]() このたび、体制強化のため 正社員の募集 を行っています。
このたび、体制強化のため 正社員の募集 を行っています。![]() 玄玄は「生活」と「リハビリ」が自然につながる関わりを大切にし、利用者さん・ご家族・地域、そして働くスタッフにとって“無理のない自由と安心”が両立する現場を目指しています。
玄玄は「生活」と「リハビリ」が自然につながる関わりを大切にし、利用者さん・ご家族・地域、そして働くスタッフにとって“無理のない自由と安心”が両立する現場を目指しています。![]()
![]() ■応募方法(ハローワーク)
■応募方法(ハローワーク)![]() 募集内容・条件などの詳細は、ハローワークに掲載しています。
募集内容・条件などの詳細は、ハローワークに掲載しています。![]() ハローワークインターネットサービス「求人情報検索」で
ハローワークインターネットサービス「求人情報検索」で![]() ▶︎ 事業所番号:3414-616460-5
▶︎ 事業所番号:3414-616460-5![]() を入力してご覧ください。
を入力してご覧ください。![]()
![]() ■見学も歓迎です
■見学も歓迎です![]() 「まずは雰囲気を見たい」という方は、ホームページのお問い合わせフォーム/お電話からお気軽にご連絡ください。
「まずは雰囲気を見たい」という方は、ホームページのお問い合わせフォーム/お電話からお気軽にご連絡ください。![]()
![]() ※この投稿を見て「合いそうな方がいるかも」と思われた方は、シェアいただけると助かります。
※この投稿を見て「合いそうな方がいるかも」と思われた方は、シェアいただけると助かります。![]()
![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #広島市南区 #広島介護 #介護求人 #正社員募集
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #広島市南区 #広島介護 #介護求人 #正社員募集
盤を挟んで、少しだけ黙る。![]() 指先が止まり、また動く。
指先が止まり、また動く。![]() そういう時間が、ここにはある。
... See MoreSee Less
そういう時間が、ここにはある。
... See MoreSee Less
■お祝いとは何か。そう問われると、たじろぐ。ケーキを囲むことか、拍手か、ラミネートか?——その問いに、ひとつの現場がささやかに答えようとしていた。1月の終わり、玄玄の午後、ある利用者さんの誕生日会がひらかれた。![]() ■準備は静かに、でも粘り強く進められていた。庭に咲いたパンジーを2週間かけて押し花にしてカードに仕立て、スタッフ一人ひとりの手書きのメッセージを添えた。さらに、ご本人の手形をとるという、あまりにも“いまこの瞬間”を記録する行為。このあたり、ただの記念品とはちがう、どうしても抗うことのできない、ある意味残酷な時間に対する、ある種の反抗が込められていた。
■準備は静かに、でも粘り強く進められていた。庭に咲いたパンジーを2週間かけて押し花にしてカードに仕立て、スタッフ一人ひとりの手書きのメッセージを添えた。さらに、ご本人の手形をとるという、あまりにも“いまこの瞬間”を記録する行為。このあたり、ただの記念品とはちがう、どうしても抗うことのできない、ある意味残酷な時間に対する、ある種の反抗が込められていた。![]() ■「〇〇さん、起きてくれるだろうか」「こちらのひとりよがりじゃないかな」そんな迷いもあったという。でも、そういう迷いをそのまま持ち込めるチームの成熟、それ自体が祝福だ。結果として、その利用者さんはゆっくりと目を開け、ほほえみ、カードを受け取った。——その笑顔に、場が吸い込まれた。まるで「現場の奇跡」という言葉をそのまま映像化したような瞬間だった。
■「〇〇さん、起きてくれるだろうか」「こちらのひとりよがりじゃないかな」そんな迷いもあったという。でも、そういう迷いをそのまま持ち込めるチームの成熟、それ自体が祝福だ。結果として、その利用者さんはゆっくりと目を開け、ほほえみ、カードを受け取った。——その笑顔に、場が吸い込まれた。まるで「現場の奇跡」という言葉をそのまま映像化したような瞬間だった。![]() ■企画したスタッフが、こんなことを書いていた。「うまくやりたいという気持ちが、現場のミラクルをさまたげることもあるかもしれない」。これは、すごいことを言っている。つまり“技術”ではなく“気配”に身をまかせようという覚悟。パンクのステージで、マイクがハウってもそのまま叫び続けるような、即興の強さ。予定調和を越える勇気。——わたしは思った。これは一種の“即興演劇”なのだ、と。
■企画したスタッフが、こんなことを書いていた。「うまくやりたいという気持ちが、現場のミラクルをさまたげることもあるかもしれない」。これは、すごいことを言っている。つまり“技術”ではなく“気配”に身をまかせようという覚悟。パンクのステージで、マイクがハウってもそのまま叫び続けるような、即興の強さ。予定調和を越える勇気。——わたしは思った。これは一種の“即興演劇”なのだ、と。![]() ■即興といえば、このとき、犬島製錬所美術館で観たインスタレーションのことを思い出した。時間の流れが、光と影と空気と鉄の匂いの中でズレていき、気づけば自分の呼吸も変わっていた。作品というより「場」そのものがメッセージを発していた。この誕生日会も、似ていた。場が場として成立し、そこで起きることはすべて、ひとつの「作品」だった。すべての利用者さんであり、すべてのスタッフでもあり、そこにいたすべての人が、それを目撃した。
■即興といえば、このとき、犬島製錬所美術館で観たインスタレーションのことを思い出した。時間の流れが、光と影と空気と鉄の匂いの中でズレていき、気づけば自分の呼吸も変わっていた。作品というより「場」そのものがメッセージを発していた。この誕生日会も、似ていた。場が場として成立し、そこで起きることはすべて、ひとつの「作品」だった。すべての利用者さんであり、すべてのスタッフでもあり、そこにいたすべての人が、それを目撃した。![]() ■“重度の方へのアプローチ”は、ともすると「届かないかもしれない」不安に苛まれる。でも、だからこそ“届いたんだと思えた瞬間”からは、大きな感動が届く。「こちらから届かせる」ではなく、「届くかもしれないことに懸ける」。その姿勢が、支援においてもっとも人間的なものなのかもしれない。力ではなく、余白でつながる。音ではなく、音の“間”でわかりあう。それはケアというより、もう詩だ。
■“重度の方へのアプローチ”は、ともすると「届かないかもしれない」不安に苛まれる。でも、だからこそ“届いたんだと思えた瞬間”からは、大きな感動が届く。「こちらから届かせる」ではなく、「届くかもしれないことに懸ける」。その姿勢が、支援においてもっとも人間的なものなのかもしれない。力ではなく、余白でつながる。音ではなく、音の“間”でわかりあう。それはケアというより、もう詩だ。![]() ■繰り返すが、その利用者さんは、笑ってくれた。その笑顔を、初めて見たスタッフもいた。それだけで十分だった。そしてその笑顔は、ラミネートされた押し花カードの中に、あの午後の光とともに、そっと閉じ込められている。——「今、その利用者さんが、確かにここにいた」ことを、わたしたちは絶対に忘れない。
■繰り返すが、その利用者さんは、笑ってくれた。その笑顔を、初めて見たスタッフもいた。それだけで十分だった。そしてその笑顔は、ラミネートされた押し花カードの中に、あの午後の光とともに、そっと閉じ込められている。——「今、その利用者さんが、確かにここにいた」ことを、わたしたちは絶対に忘れない。![]() 藤渕安生
藤渕安生![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #介護現場 #重度ケア #誕生日会 #介護の奇跡 #即興演劇ケア #気配のケア #現場から生まれる物語 #介護職とつながる
... See MoreSee Less
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #介護現場 #重度ケア #誕生日会 #介護の奇跡 #即興演劇ケア #気配のケア #現場から生まれる物語 #介護職とつながる
... See MoreSee Less
話の途中だったか、それとも終わったのか。 ![]() どちらでもいい気がする。
どちらでもいい気がする。 ![]() ただ隣に座り、同じ時間を吸い込む。
ただ隣に座り、同じ時間を吸い込む。 ![]() 冬の陽ざしだけが、床の上を動いていた。
... See MoreSee Less
冬の陽ざしだけが、床の上を動いていた。
... See MoreSee Less
アクセス
住 所 :広島市南区東雲2丁目7番17号